開業医が手取り年収を増やすための考え方
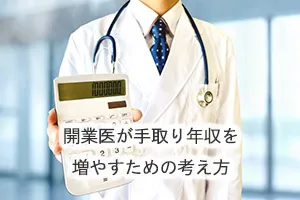
これからクリニックを開業しようとする先生の多くは、ご自身の手取り年収がどれくらいになるのか、気になる方が多いと思います。そこで、開業医が効果的に手取り年収を増やすための考え方をご説明いたします。
クリニックを開業した後では、先生の手取り年収を増やそうと思っても意外と難しいものです。なぜなら、開業してしまうとテナントの契約やスタッフの体制など、多くの要素が固定化されてしまい、変更したくても自由度が下がるからです。そのため、手取り年収を増やしたい場合には、クリニックの開業前の事業計画づくりの段階で、入念な事業収支のシミュレーションを行うことが重要です。
ここでは、開業医として手取り年収を増やす為の基本的な考え方をご紹介します。
クリニックを開業して、効果的に手取り年収を増やしたい先生は、ぜひ最後までご覧ください。
手取りと年収の違い
手取りとは、最終的に現金として手元に残る金額のことです。年収は、税務署に申告する最終利益(所得)のことです。手取り年収は、所得から税金や社会保険料などを引いた、最終的に手元に残る金額です。そのため、所得よりも手取り年収の方が金額が小さくなります。
一般的な開業方法でしたら、所得よりも手取り年収が増えることはありません。ところが、医師優遇税制を利用した開業方法ですと、所得と手取り年収が逆転し、手元に残る金額を大幅に増やすことができます。
この記事では、開業医が手取り年収を増やす方法を解説いたします。
手取り年収計算の基本

手取り年収を計算する上で、基本となることをお伝えしたいと思います。クリニックを開業しようとなさっている先生は、これから経営者になるわけですから、クリニック経営にとって大切な収支の解説に少しお付き合いください。
手取り年収の計算式
手取り年収は、入ってくるお金と出ていくお金の差で決まります。計算式は次の通りです。
手取り年収 = 入ってくるお金 - 出ていくお金
入ってくるお金は、基本的には患者さんからの診療報酬ですが、例えば、皮膚科クリニックの場合にはスキンケア用品などの物販をしたときの収入もあります。基本は自費診療と保険診療の収入ですので、入ってくるお金の計算式は次のようになります。
入ってくるお金(売上高) = 自費収入 + 保険収入 + 物販での売上
物販での売上高は、自費収入や保険収入からすると微々たるものですから、基本は患者さんの診療報酬が売上高となります。これらの収入は診療単価に患者さんの人数をかけたもので集計することができます。
売上高 = 自費単価 × 人数 + 保険単価 × 人数
皮膚科であれば、通常自費単価はおおよそ1万円、保険診療の単価は3,000円程度に見ておいた方が良いでしょう。
次に出ていくお金ですが、固定費と変動費が基本です。他にも、税金や社会保険料、スタッフを雇用したときの費用、クリニックの内装を修理したときの費用などがありますが、それらをその他の費用としてまとめると、出ていくお金の計算式は、次のようになります。
出ていくお金 = 固定費 + 変動費 + その他の費用(税金・社会保険料など)
固定費と変動費
固定費とは、患者さんの数とは関係なく、毎月固定でかかる費用のことです。例えば、家賃や人件費、光熱水費などが固定費となります。
光熱水費は、厳密に言えば患者さんが多ければ、それだけ水道代や電気代もかかりますが、患者さんが多くても上昇する光熱水費は微々たるものですから、固定費として扱います。スタッフの人件費も同様に、患者さんの数が多くなれば、スタッフをたくさん雇うので、たくさんの人件費がかかるようになりますが、「患者さんの数が減ったから」といってすぐに解雇できませんから、固定費として扱います。
変動費とは、患者さんの数に応じてかかる費用のことです。患者さんの診療にかかる医薬品や検査の外注費などは、患者さんの人数が多ければたくさんかかり、少なければその分だけ使用しませんから費用がかかりません。そういったものは、患者さんの人数に比例して変動しますので、変動費といいます。
売上高から変動費を引いた利益のことを、売上総利益とか粗利益といいます。
売上総利益 = 売上高 - 変動費
売上総利益が固定費の金額を超えると、クリニックが黒字になり、固定費の方が大きい場合には赤字です。売上総利益と固定費の金額が同じになるときの売上高が、損益分岐点です。
売上総利益 > 固定費 ⇒ 黒字
売上総利益 < 固定費 ⇒ 赤字
固定費が低いほど、患者さんを診察する人数が少なくても黒字になりやすいので、経営リスクが低くなります。
手取り年収を増やすための基本戦略

上記の式から、手取り年収を増やすための基本戦略は、売上高を増やし、出ていくお金を減らすことです。
売上高を増やす
売上高は、基本的に自費収入と保険収入の金額で決まります。それらの金額は、診療単価と患者さんの人数によって決まります。売上高を増やすためには、診療単価を上げる方法と患者さんの人数をふやす方法、もしくはその両方があります。
皮膚科であれば、自費単価は1万円、保険診療の単価は3,000円程度とご説明しましたが、保険単価は厚生労働大臣によって定められた医科診療報酬点数で決まっているので、むやみに上げることはできません。保険単価を上げる方法は、初診患者さんの比率を上げて必要な検査・処置を行うことです。
自費診療の単価は、院長の判断で上げることは可能です。しかし、それでも限界があるので、患者さんの人数をふやすことを基本とすべきです。患者さんの数は、新規の患者さんとリピーターの患者さんがいます。
患者さんの数 = 新患 + リピーター
基本的には新規の患者さんの獲得を第一に考えるべきですが、一般的には患者さんの登録数が3,000件を越してくると、登録された患者さんの中で一定数の再診患者さんが来院してくる様になります。
慢性疾患を専門とする糖尿病内科や循環器内科などは、長期的に診察や治療を続けるので、リピーターの患者さんに重点を置くことが大切です。
出ていくお金を減らす
出ていくお金を減らす方法は、固定費を減らすことが基本となります。なぜなら、変動費は患者さんの来院数に連動するので下げることができたとしても限界があるからです。
固定費の中で大きな金額を占めるものは、テナントの家賃と人件費です。テナントの家賃は、最初に契約した金額がそのまま継続するため、クリニックを開業するときに決まります。ですから、なるべく家賃の総額が安いところを探すことで、固定費を下げることができます。
人件費は、スタッフを常勤ではなくパートスタッフを雇うようにしたり、できるだけ少ない人数でクリニックを運営していくことで下げることができます。
手取り年収を増やすための対策は単純にはいかない
患者さんの数を増やすことと、出ていくお金を減らすことのどちらかを行うとするならば、患者さんの数を増やすことが基本です。しかし、クリニックを開業してしまったら、その後から患者さんの数を増やしたり、出ていくお金を減らしたりする対策を取ることは困難である場合が多いです。
また、さまざまな対策を行ったとしても、そもそも集患が難しい場所で開業していたり、経費を節減することが難しい様なシステム作りをして開業されていた場合には、対策にかけた費用の割には効果を出すことが少ないために、固定費の節減は簡単には行きません。
本来は、クリニックを開業する前に、先生ご自身が開業医となられて何を目指されるのか、どのような人生計画を立てるのかを考慮しながら、さまざまな条件で入念に事業収支のシミュレーションを繰り返すことが大切です。
クリニックの大きさで患者さんの来院数の上限が決まる

売上高を増やして手取り年収を増やす方法の一つに、たくさんの患者さんに来院してもらい、受診者数を増やしていく方法があります。ところが、クリニックの広さも限界があるので、院長一人で診察するのでは患者さんを診察する数にも上限があります。
仮に、クリニックを開業したときに、テナントの家賃の安いところを借りていたとしましょう。賃貸料が安いと言うことは、次のうちのどちらかです。
- クリニックの坪数が小さい
- 立地が悪くて患者さんに認知してもらいにくい場所にある
クリニックの家賃は、テナントの坪数と坪単価を掛けた金額です。クリニック賃貸料が安い場合には、テナントの面積が狭いか、賃料の坪単価が安いかのどちらかです。
テナントの家賃 = 坪数 × 坪単価
テナントの面積が狭い場合には、待合室や診察室も狭く、スタッフの人数も増やせないので、多くの患者さんを診ることができませんから、患者さんの数を増やそうとしても限界があります。
坪単価の安いテナントは、人通りの多い所から離れた場所にある場合が多いです。そういった場所では、患者さんから認知されにくい場所であったり、駅から離れた場所で通院するためには不便な場所にあったりします。そういった集患がしにくいクリニックで、患者さんの数を増やそうとしても限界があります。
クリニックを開業するときに、坪単価が高いけれども集患がしやすく、坪数の広いテナントを借りて、「将来的に常勤の医師を雇って、たくさんの患者さんを診られるようにしたい」と考えたとしましょう。すると、開業当初は患者さんの人数が少ないため、常勤の先生を雇えるくらいに患者さんの数が増えるまでは、賃貸料が重くのしかかります。
もし患者さんの数が増えなければ、テナントの家賃を払うために働いているように感じることもあり、先生のモチベーションが下がってしまうこともあります。そのまま患者さんの数が増えずに、赤字が続けば、倒産することもあり得ます。
クリニックの引っ越しは難しい

患者さんが多く来院してくれるようになり、さらに人数をふやして売上高を増やすためには、今のクリニックの広さでは手狭だったとします。先生によっては、「もっと広いテナントに引っ越しをしよう」と考えるかもしれません。
また、クリニックを経営していて「患者さんが増えないのに、テナントの家賃が高い」と感じる場合もあります。そういった場合には、家賃の安い場所に引っ越しをしたくなると思います。
ところが、クリニックの引っ越しは一般的には難しい場合が多いです。
まず、引っ越し先となる手頃なテナントが見つかるかどうかです。テナントはすぐに見つかるわけではありません。現在診ている患者さんに、引き続き来院してもらいたいのであれば、引っ越し先は近所に限定されますから、なおさら見つけにくくなります。
近所に引っ越しができたとしても、その場所で患者さんがさらに増える保証はありません。
引っ越しのためには、新しく入居するテナントの内装工事が必要ですし、引っ越しをした後は、今いるテナントをスケルトンに戻す工事も必要となります。そのための費用は、金融機関からお金を借りることになりますが、事業計画を立て直す必要もあります。
スタッフの人件費を下げられたら手取り年収を増やせるか?

スタッフの人件費や人数を下げられ、なおかつ患者さんの数が減らなければ、先生の手取り年収を増やすことは可能です。短期的には手取り年収が増えたとしても、長期的には減ってしまう場合もあります。
最近は働き手市場
最近はクリニックで働きたいと考えている人の数が、求人数よりも少ないということが現状です。クリニックや病院での看護師の有効求人倍率は2倍を超えているようですから、働き手市場と言えます。つまり、お給料を高く設定するなどの条件を良くしないと、スタッフを雇うことが難しくなります。医療事務の専門スタッフを雇いたい場合にも同様です。
経営者としては、人件費を下げたいのでパートスタッフを雇いたいとお考えになることが多いですが、働き手として求職する人は常勤スタッフとして働き、高いお給料や社会保険などを求めます。クリニックで働きたい人は、地域のクリニックの求人情報を見て、条件の良いところを選ぶので、少なくとも、地域のクリニックの求人条件を確認しておくことが大切です。
スタッフの採用でかかるコスト
仮に求人の条件が悪かったとすると、スタッフを雇うことができなくなる場合もあります。スタッフを雇うことができなければ、クリニックの業務が滞り、患者さんへの対応が悪くなる可能性がありますので、患者さんからの評判も悪くなって、来院する患者さんの数が減ってしまう可能性もあります。
もちろん未経験のスタッフを雇って教育することによって、サービスを向上させることも可能だと思いますが、教育に時間を取られるようになりますし、スタッフが慣れるまでは、患者さんを診られる人数を維持することも難しくなります。
さらには、クリニックの業務に慣れてきたところで、他のお給料の高いクリニックに転職していってしまう場合もあります。そうなると、また新しくスタッフを雇い教育しなければいけません。スタッフを雇うためには、求人のための広告費もかかりますから、先生の手取り年収を下げてしまう可能性もあります。
スタッフのお給料は、少なくとも地域のクリニックよりも少し高めに設定しておき、社会保険への加入も検討すべきでしょう。さらに、新規開業を予定しているクリニックの場合は、少なくとも1名は経験者を雇って、経験の少ないスタッフに仕事を教えてもらえると理想です。
スタッフの人数を減らすと手取り年収を増やせるのか?
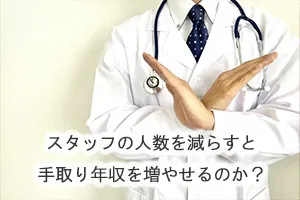
スタッフの人数を減らせるということは、スタッフが育ち、効率よく業務ができるようになってからとなります。また、その効率の良い業務をルール化やマニュアル化して、新しく入ったスタッフを、ベテランスタッフが丁寧に育成できるようになってからです。
クリニックを開業した当初は、あらゆる業務が不慣れなところから始まりますから、小さなクリニックでも受付には2名ほどスタッフがいると安心です。スタッフが2名いたとしても、少ない患者さんの来院でさえバタバタするものです。少しずつ業務になれていってから、患者さんの数を増やし、3年目で患者さんの数が想定人数に達するようになることが理想です。
1年も業務を経験すると、スタッフ全員が仕事に慣れてくるので、小さなクリニックの場合には受付は1名でもできるようになるかもしれません。また、完全予約制にするなどして、先生が採血や検査などの対応ができるようになっていると、場合によっては受付スタッフが1名でも業務を回すことができる場合もあります。実際に、スタッフが1名で先生の手取り年収が2,500万円を超えている先生もいらっしゃいます。
スタッフの人数を減らすときは、スタッフを解雇するのではなく、スタッフが辞めていくときがタイミングとなります。しかし、残されたスタッフはその穴埋めのため業務量が増えますから、スタッフから「人数を増やして欲しい」という要望がある場合もあります。そうした場合には、パート勤務の可能なスタッフを採用して、業務量を平均化することでクリニックの業務に混乱が起きない様に注意することが大切です。そうしないとスタッフに不満が溜まってしまい、良いスタッフが辞めてしまう可能性もあります。残りのスタッフに辞められてしまったら、クリニックの業務が滞って混乱しかねません。
スタッフの人数が少なくなり、作業量が増えた場合には、お給料を上げることも必要です。
医師優遇税制を活用して手取り年収を増やす
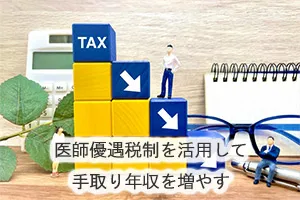
医師優遇税制とは?
冒頭で、出ていくお金の中に「その他」という項目がありました。その中には、税金も含まれています。その税金を節税して手取り年収を大幅に増やす方法があります。その方法とは、医師優遇税制(租税特別措置法第26条)を活用することです。
この法律を要約すると、「年間の自費収入の上限が2,000万円以下、かつ保険収入の上限が5,000万円以下であれば、経費を売上高の70%ほどで申告しても良い」という法律です。
この法律を活用すると、なぜ手取り年収が増えるのかをご説明いたします。
どれくらい手取り年収が増えるのか?
例えば、内科クリニックを開業し、外来収入が5,000万円だったとします。そして固定費と変動費の合計が2,000万円かかったとします。その差額が経常利益となります。
経常利益 = 年間の売上高 - 年間の費用
すると経常利益は3,000万円となりますが、それに所得税や住民税などが一定の割合でかかります。また、クリニック開業当初は金融機関に借入金を返済する必要もあります。それを引いたものが先生の手取り年収になります。経常利益が3,000万円ですと、各種の控除を差し引いた上で税金等として1,000万円ほどの支払いが必要となりますので、先生の手取り年収は2,000万円ほどになります。
ところが、医師優遇税制を活用して確定申告をすると、5,000万円のうち「約70%の費用がかかった」と見なすので、約3,500万円の経費がかかったと申告をします。すると、経常利益は1,500万円に減るため、支払う税金も300万円ほどになるので、その分だけ先生の手取り年収が増え、手取り年収は2,700万円となります。
また、申告は簡単な計算だけでできるので、税理士に依頼する必要はありませんから、その分の費用を100万円ほど節約できるので、その分も手取り年収が増え、2,800万円ほどになります。この計算はあくまでも概算ですから、実際に近い数値で収支シミュレーションを繰り返すことが大切です。
医師優遇税制の活用について詳しく知りたい先生は、「特措法とは?クリニック経営する医師だけに認められたお得な税制」をご参照ください。
開業前に入念な事業の収支シミュレーションを繰り返すことが最重要
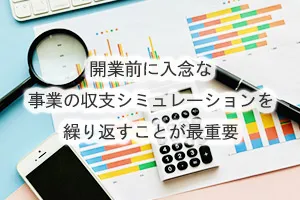
クリニックは入居するテナントによって、色々な制約を受けてしまうことをご理解いただけたと思います。クリニックの開業場所を選ぶことが、先生の手取り年収を決める要素になるだけでなく、その後のクリニック経営のリスクの高さも決まります。
手取り年収を高くするためには、先生が長時間働き、非常勤の先生も雇って、たくさんの患者さんを診る必要があります。そうするためには、立地条件が良くて広い面積のテナントを借りる必要があります。
反対に経営リスクを下げて、患者さんの来院数が少なくても黒字になりやすく、なおかつ医師優遇税制を活用して手取り年収を増やしたい場合は、できるだけコンパクトなクリニックにすることをおすすめします。
どちらにしても、テナント家賃の坪単価が高くても、集患がしやすい場所での開業が望ましいです。
クリニックの開業を考えたら、先ず開業コンサルタントに相談されると思います。開業コンサルタントの力量の一つに、「どの場所に開業すると、どれくらいの患者さんの人数になりそうか」という判断があります。よくある診療圏調査はあくまでも目安なので、あまり集患ができないと判断される場所であっても、充分に黒字経営ができる場合もあります。
そのようにして開業予定地の集患の可能性を考慮しながら、先生がどのようなライフプランをお考えなのかも考慮することで、最適なクリニックの規模が想定されます。それを元にして、さまざまに事業の収支シミュレーションを行い、具体的な事業計画を立てることが最重要となります。
当社では、東京23区やその周辺都市での開業を目指される先生に向けて、開業支援サービスをご提供しております。当社にコンサルティング契約を依頼なされるかどうかに関わらず、「これから東京やその周辺都市で開業したい」とお考えの先生に、無料で事業の収支シミュレーションをしております。
まずは当社で行っている無料のクリニック開業Webセミナー&個別相談会にご参加ください。このセミナーでは、先生が開業によって実現したい人生プランや開業についての悩み相談などにも対応しています。
先生からのお問い合わせをお待ちしております。



