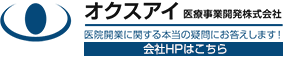小児科医院の開業を支援する
クリニック開業コンサルティング
クリニック開業の失敗を未然に防ぎ、
開業直後から利益が出るクリニックを目指す
初めてクリニック経営をされる医師に寄り添ったコンサルティング
- 35年の実績
- トータルサポート
- はじめての経営でも安心
開業準備から
クリニックが軌道に乗るまで
ワンストップ支援
小児科クリニックの新規開業支援なら、
コンサルティング実績豊富なオクスアイにご相談ください。
当社では、クリニック開業のアドバイスはもちろんのこと、
クリニックの事業計画(経営計画)立案、クリニックの内装工事支援、
開業時のご支援、人材教育、開業後の経営相談などに対応しています。
クリニック開業までワンストップでコンサルティングができることが、
当社の強みです。ワンストップ支援であることが、 クリニック開業で
失敗しないポイントです。
小児科クリニックの低リスク開業は、医師としてのキャリアと
子育てを両立させる、ワークライフバランス開業にも最適です。
小児科クリニックの開業を目指されている医師は、
開業予定の1年以上前にご相談いただくことをおすすめします。
小児科クリニックの
開業で
失敗しないための
4つのポイント
当社では、女性医師からの小児科クリニック開業のご相談依頼が増えてきました。科目柄、産婦人科と同様に女性医師の方が有利である傾向があります。男性医師の場合には、女性医師に比べると性別による若干のハンデはあるものの、子どもや親御さんの気持ちを第一に考えた診療姿勢を大切にすることで、小児科クリニックの開業を成功させることができます。
また、アレルギー科や皮膚科などといった複数の科目を組み合わせたクリニックを開業することで、幅広く子どもの症状に対応でき、安定経営につながります。
クリニックの開業は、医師の仕事をしながら数多くの手続きが必要なので、外部支援がなければできるものではありません。誰に外部支援をしてもらうかの選択が、小児科クリニックを成功させるための最初のポイントになります。
小児科クリニックの開業で失敗しないためには、特に次の4つのことが大事になります。
- ワークライフバランスを考えた開業のタイミング
- 小児科医院に適切な立地の選定
- 感染症対策のための隔離診察室と導線の分離計画
- 血算・CRPなどの緊急検査機能の装備
このページの後半で、これらの内容を解説しています。
当社のクリニック開業
コンサルティング支援
- 開業相談
- 開業候補地の
選定 - 医療需要調査
- クリニック開業
準備支援 - 内装工事の
設計・施工支援 - 集客のプロ
モーション支援
当社の開業コンサルティングの特長
医師の立場で事業計画を立案
開業コンサルティングの多くは、医療機器メーカや医薬品卸業者が行っており、自社製品が売れることを前提として支援します。そのような企業はアドバイスに偏りがあります。当社は、純粋な開業コンサルなので、医師の立場でワンストップで支援いたします。
内装設計にも強い
多くの開業コンサルタントは、自社が扱う分野のことは詳しいのですが、ほとんどの方が内装設計のアドバイスができません。内装設計はクリニックを長年運営する医師にとって、大事な部分です。人生計画に沿った使い勝手の良い内装設計提案ができるのも当社の強みです。
トラブルを未然に防ぐ
一般的なコンサルタントは、トラブルがあった後に相談を受ける方針です。なぜなら、先に起こるであろう事態の見通しが甘いからです。当社では、開業コンサルティング支援の中で、事前にトラブルの元をつみ取り、何百万円以上もの損害を未然に防いだ事例も数多くあります。このように費用対効果の良さに定評があります。
オクスアイと他社コンサルタントの比較
| オクスアイ | 他社コンサルタント | |
|---|---|---|
| 支援内容 | ワークライフバランスのご相談、実績に基づいた事業計画の立て方や資金計画のシミュレーションといったご支援から、内装工事、開業手続き、内覧会など、開業に関わるすべてのことをアドバイスいたします。 | 薬局・医療機器メーカーや税理士など、限られた分野にのみ精通しているコンサルタントが多いです。 |
| ミニマム開業 | ミニマム開業に数多くの実績があります。特措法第26条に基づいた開業支援も当社の強みです。 | ミニマム開業どころか、特措法第26条の存在を知らない開業コンサルタントも多いです。 |
| 開業後の経営相談 | 開業後は無料でご相談に対応しています。お気軽にご相談ください。 | 開業後の経営相談は有料であったり、「専門外です」と言う開業コンサルタントが多いようです。 |
| 開業場所の提案 | 開業場所の選定は事業の成功に大きな影響を与えます。開業場所の選定は、実績に基づいて「先生に合った良い場所」が見つかるまで開業を待っていただくようにしています。 | 開業場所と事業の成功が大きく関わっていることを知らず、どの物件を見ても「いいですね」としか言わない人や、空いているテナントを探すだけの開業コンサルタントもいます。 |
| 内装工事 | クリニックの設備や内装に精通した開業コンサルタントが、内装工事プランをご提案いたします。 | 消防法や建築設備のことを知らない開業コンサルタントが多いです。 |
小児科クリニック
開業支援実績
自分ですべて一から始めるのは無理だったろうと思います
澤田こどもクリニック(小児科、小児アレルギー科)
澤田雅子先生
東京都文京区
知人の開業医は薬の卸会社系列の開業コンサルタントに依頼していたのですが、自社の製品を買わなければならないなど、いろいろな制約があって大変そうでした。オクスアイさんは、開業コンサルティングとクリニック施工を専門にやっているため、中立的な立場で支えていただけました。迅速に対応してくれたり、相談しやすいのが有難いです。
子育てと仕事の両立がしやすいです
クローバーこどもクリニック(小児科)
眞々田容子先生
東京都台東区
小学校・公園にも隣接しているため、お母さんの目にも留まり、家から近く、クリニックの前の小学校に娘が通っているので、子育てと仕事の両立がしやすいです。開業に向けての情報はほぼゼロからでしたし、クリニックをどうやって作っていくかもわからなかったので、アドバイスすべてが参考になりました。
率直に言ってくれるので、アドバイスも信頼できると思いました
小石川柳町クリニック(小児科・内科)
近藤千里先生
東京都文京区
開業コンサルティングのサービスと建築事務所が別だと、それぞれ話を通すのも面倒ですが、オクスアイさんは建築に関してもプロなので、クリニック建築の話を直接進めていけるのが良かったです。参考になったアドバイスはいろいろありますが、特に助かったのが、コストをかけない提案をしてくれたことでした。
コンサルティングの流れ
開業を決めてからの
無料コンサルティング
開業セミナー&相談会
まずは、無料セミナーにご参加ください。開業直後の集患と経営に差が出るクリニック開業準備についてご説明いたします。ご希望の開業スタイルや悩みをご相談ください。
無料開業相談
開業の迷いや疑問な点など、何でもご相談下さい。事業計画のシミュレーションで、開業の成功とリスク排除のプロセスに関して数字で見ることにより、開業の具体的なイメージを持つことが出来ます。
開業場所の選定
医師のご希望に沿って開業場所の地域を絞り込み、医師とコンサルタントが協力して物件を探します。候補となる物件を選定して、コンサルタントが同行して適性をアドバイスしますのでご安心ください。
開業場所が決まってからの
有料コンサルティング
事業計画・資金調達
開業場所が決定したら事業計画が立てられます。融資を受けるために、利益が出る資金調達用と、手堅く失敗しない経営用の2種類の事業計画を策定することが当社のノウハウです。
内装の設計・施工
別途費用になりますが、内装工事の設計・施工を当社にて行っています。コンサルティング業務と連携することで無駄をなくし、先生にご負担をかけないクリニック創りを実現します。
開業手続き・プロモーション
保健所・厚生局などの関係部署との事前協議や申請をサポートします。また、医院のPRやスタッフ募集・集患のためのプロモーションをサポートします。
開業直前準備・経営管理
医薬品や医療機器の準備をサポートしつつ、スタッフの募集から面接・採用・就業規則をご提案し、開院準備期間中に於ける職員教育と経営管理のアドバイスを行います。
開業後のコンサルティング
開業前後
開業前後では、地域へのPRや内覧会の案内や開催、実施方法などについても具体的にサポートをいたします。
開業後の問題
開業後は、人の問題や経営の心配事が出てくるものです。実際に経営を始めることによって出てくる問題に、丁寧にアドバイスとサポートをいたします。
主な開業支援エリア
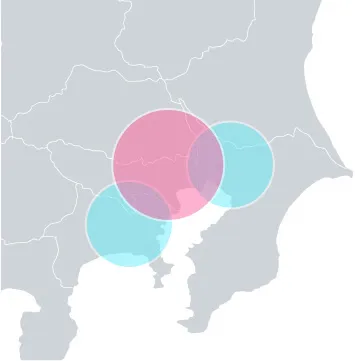
当社では、都内を中心として、主に神奈川県、埼玉県、千葉県の東京都近郊をサービスエリアとして、小児科クリニックの開業をご支援しております。
サービスエリア外での開業の支援実績もございます。エリア外で開業をご検討されている医師でも、お気軽にご相談ください。
主な開業支援エリア
- 東京都
- 神奈川県
- 埼玉県
- 千葉県
コンサルティング費用
クリニック開業【無料】コンサルティング
費用
開業検討での業務は無料です。
コンサルティング内容
開業相談
開業に関する迷いや疑問な点など、何でもご相談下さい。
事業計画のシミュレーションをお試し頂きながら、開業の成功とリスク排除のプロセスに関して具体的なイメージを持つことが出来ます。
開業場所の選定
ご希望の地域を実際に回り物件の調査をし、マーケティングと施設の特性を把握しながら、先生の構想を実現する最適な開業場所をご提案します。
診療圏調査
開業場所の医療環境と人口構成など、最新データと現場の競合調査などを基に開業立地のポテンシャルを把握し、来院する患者数の推計を行います。
特に地域特性を把握した上で、安定した経営の要となる集患対策をご提案します。
以上の考察の結果、開業が決定した時点からは、下記の支援業務を開始することとなりますので、ここから有料のコンサルティングをお願いしております。
医院開業【有料】コンサルティング
費用
開業サポート業務 一括料金
1,600,000円(税別)
コンサルティング内容
事業計画
開業場所の特性を基にして、必要な資金の算出による予算案を作成して、開院後の収支予測と月別の資金繰りを検討します。 ここでクリニックの事業構想と、将来にわたる運営の青写真を検証することが出来ます。
資金調達
無担保・無保証人で調達可能な、低金利な事業資金や、日本政策金融公庫などの公的融資など、先生の状況に適した資金調達の実現をお手伝い致します。
新規開業に係わる関係官庁との調整
クリニックの開設と保険医療機関の指定をスムースに取得するために、 保健所・厚生局などの関係部署との事前協議を綿密に行い、各種申請のサポートを行います。
外注業者との契約条件などの調整
医薬品購入や外注検査など、開業後に継続して取引を行う外注業者との契約条件を有利に取り決めるための調整を行います。
職員の採用・処遇・教育
職員の募集から面接・採用へのプロセスをサポートします。 給与を始めとする職員の処遇と就業規則をご提案し、開院準備期間中に於ける職員指導を行います。
経営安定化への企画と指導
患者獲得に関する経営戦略と、クリニックの運営指導、開院のためのスケジュール管理など、院長として必要なクリニックの経営ノウハウを指導致します。
小児科
開業セミナー&相談会(無料)
ご案内

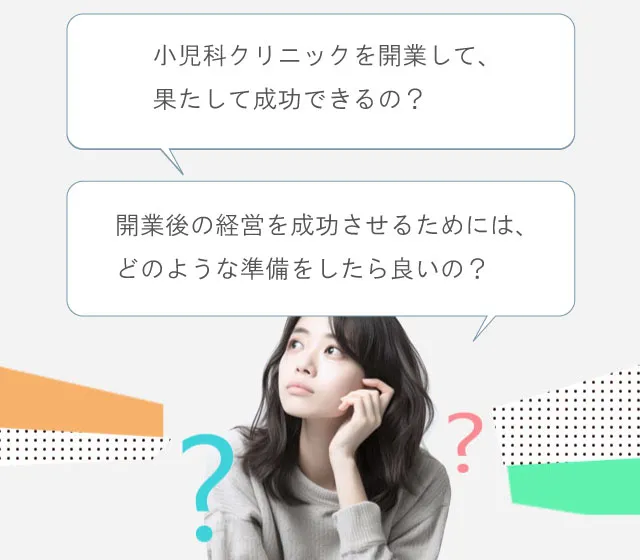
小児科開業セミナーでは、そのような疑問を抱かれている医師の先生方へ向けて、開業の資金調達や申請などの流れ、開業後の医院経営の実態と、成功するための集患方法についてお話します。
医院開業をサポートして35年以上の実績を持つコンサルタントである弊社代表が、長年の経験と実績に基づいたノウハウをお伝えさせて頂きます。
また、セミナーの後半では個別相談も受け付けますので、現在疑問や不安に思われていること等、何でもご相談ください。
開業セミナーの主な内容
| 前半 | セミナー (30分程度) |
|
|---|---|---|
| 後半 | 個別相談会 (30分程度) |
先生のお悩みや聞きたいことなど、リクエストにお答えします。 |
個別相談会でよくあるご相談
人生設計相談
- 開業すべきかどうかのご相談
- 夫婦で開業すべきかのご相談
- 女性医師の子育てしながらの開業ご相談
(仕事と子育ての両立やミニマム開業) - 定年後の開業による人生設計
開業準備相談
- 開業場所のご相談
(自宅近くでの開業、都心での開業など) - 開業資金・融資の相談
(開業にいくらかかるのか、融資を受けられるかなど) - 集患に関するご相談
- スタッフに関する相談
(マネジメントや労務管理など)
よくあるご質問 Q&A
- 最短でどれくらい前に依頼をしたらいいのでしょうか?
-
コンサルティングのご依頼は、開業予定の1年前くらいにはご依頼ください。
スムーズな資金調達や集患を考えた安定経営には、準備に2~3年の期間がかかる場合もあるので、なるべくお早目にご相談ください。
- コンサルティング費用はいくらでしょうか?
-
コンサルティングには、無料コンサルティングと有料コンサルティングがございます。このページのコンサルティング費用をご覧ください。
- 開業して集患ができなくて、失敗した先輩がいます。コンサルティングをお願いしたら、小児科クリニックでも、黒字経営にできるでしょうか?
-
その先輩は、間違ったコンサルティングを受けていた可能性があります。当社の小児科クリニック開業コンサルティングは、35年間のコンサルティングの中で失敗した先生はいらっしゃいませんので、ご安心ください。
クリニックを開業して失敗してしまう主な要因は、「クリニック経営で失敗する理由は何か?」をご覧ください。
- 小児科クリニックの開業は、少子化の影響で難しいと聞いています。開業コンサルティングをお願いしたら、都内で開業しても黒字にできますか?
-
もちろん、ファミリー世帯の少ない地域で開業してしまったら、小児科の需要が少ないので、赤字になってしまう場合があります。先生の専門性や開業場所の特性など、さまざまな要因を考慮して、先生のクリニックが黒字になるような場所選びをご支援いたします。
- 今まで経営をしたことがないので、クリニック経営に自信がありません。クリニック経営(マネジメント)のアドバイスもしてもらえますか?
-
もちろんアドバイスさせていただきます。
集患、スタッフさんの採用や育成、借入金の返済など、クリニック経営に携わると、初めて経験することがたくさんあり、悩みが多いものです。当社のコンサルティングは、そういった先生と伴走しながらのご支援を大切にしています。
分からないことは、丁寧にご説明いたしますので、安心してコンサルティングをご依頼ください。
- 女医なのですが、子育てをしながら開業ができると聞きました。小児科でも可能でしょうか?
-
今まで女性の先生が子育てをしながらキャリアを維持するというワークライフバランスのご支援を多くさせていただき、ご好評をいただいています。
小児科は、子育てと仕事を両立させるのに相性の良い科目です。お子様の通学の場所と開業場所も考慮しつつ、利益が出るミニマム開業で子育てとキャリアを両立させられる人生プランをごいっしょに立てましょう。
- 無料の開業セミナーに参加したら、コンサルティングをお願いしないといけませんか?
-
もちろん当社の開業コンサルティングをご利用いただけたら嬉しく思いますが、必須とはしておりません。
クリニック経営の成否は、開業前にほぼ決まります。当社の開業セミナーの目的は、小児科クリニックを開業された先生が、クリニック経営で失敗しないような知識を身に着けていただければ幸いです。
開業セミナー&相談会にご参加いただき、当社の開業コンサルティング支援が必要だとお感じになられたら、ぜひご利用ください。
小児科クリニックの
開業で
失敗しないための
ポイントとは?

金村 伯重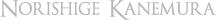
コンサルタント
一級建築士
経歴
昭和54年 病院システム開発研究所 入社
東京医科大学病院、焼津市立病院、富士市立中央病院、沼津市立病院、富士宮市立病院などの建替計画に参画 昭和59年 医療機構開発株式会社 入社
町立浜岡病院(現御前崎市立病院)新設に参画 昭和63年 オクスアイ医療事業開発株式会社設立
以来35年以上に亘り、数多くのクリニック開業をサポートしている。
総合病院であらゆる診療科目の医療現場に携わり、多岐に亘る分野の技術に精通する。また一級建築士である事から、施設造りまで自社で一貫して行う。クリニック開業を成功に導くソフトとハードの技術を確立し、他に例を見ないコンサルティングを実践。これまでサポートしたクリニックを全て成功に導いている。
小児科の女性医師が増加傾向
これまで私共が開業コンサルティング支援をしてきた小児科医院の中では、割と女性の先生方の比率が高かった様な感じがいたします。
医師全体の総数の中ではやはりいまだに男性医師の方が多いので、小児科に限らず多くの診療科目の中でも同じように男性医師の割合が多いのが普通ですが、小児科を専門分野として選択する医師の中では、徐々に女性医師が占める割合が増えてきているのではないでしょうか。
近年医学部に進学する学生さんの中でも、女性の割合が増加してきています。女子高校の御三家などと言われる有名進学校などでは、トップクラスの学生さんの多くが医学部への入学を目指していると言われています。
もともとご両親が医師や開業医であったり、ご親戚にドクターの多い家系であったりする事で、医学部を目指す事が当たり前の環境に育ってきたという学生さんも多いことだと思います。
それに加えて、有名進学校から医学部に進学するというコースを進める家庭環境の中で育つということは、学生さん本人の学力が優れているということだけでなく経済的にも恵まれた家庭に生まれてきたということでしょう。
そのような家庭環境の中で育った女性が、将来的にも自立して生きられる道としては、医師の資格を取得することが理想的な選択肢なのかもしれません。
大学医学部の教育課程を終えて、医師の免許を取得してから初期研修で各診療科のローテーションを経験する中では、女性医師として馴染みやすい診療科目と、そうでもない診療科目があると思います。
個人的な考え方もあるかとは思いますが、一般的には内科・小児科・産婦人科・皮膚科・眼科などを専門科目として選択する傾向が大きいように思います。
そうした中でも、小児科と産婦人科は母性につながりやすい事から女性医師の割合が増えてきたように思います。
ワークライフバランスを考えた開業のタイミング
女性医師が開業をしたいと考えるタイミングは、結婚や子育てのときです。勤務医では結婚はできたとしても、ワークライフバランスが取れないことがほとんどです。そして、子育てのために休職をした場合にはキャリアがリセットされる可能性もあります。
そういったときにお勧めの方法が時短開業です。小児科医院はお母さん方の行動時間に合わせられる事から、特に時短開業のしやすい診療科目とも言えます。そして、お子様が成長して学費が必要になればガッツリ働くこともできます。
家庭を大切にし、子育てをしっかり行うことができる時短のミニマム開業のアドバイスは、当社オリジナルのコンサルティングです。
小児科医院に適切な立地の選定
一般的なクリニックの立地条件としては、多くの患者さんが獲得できる駅前や商店街なとの繁華街が最上とされています。
普通の診療科では大人の患者さんを対象としていますから、コンビニやカフェなどを開業する際の立地条件を選ぶ場合と同じように、クリニックの前をより多くの不特定多数の人たちが通行するような立地を選ぶことが成功のポイントと言えます。
ところが小児科医院の場合には、そのような選定基準とは少し違ったところがあります。
例えば、駅前や繁華街に小児科医院が有ったとして、お母さんたちはお熱が出ている赤ちゃんや小さな子供さんを連れて、そのような場所にある小児科医院に安心して通えるでしょうか。
大人が通いやすいクリニックの場所
大人の発熱や病気の場合には、ある程度の自己診断を加えながら、通院するのにより便利な場所のクリニックを選んで受診することが多くあります。大人の場合には、これまで過ごしてきた人生経験から、自分の体の調子や病気の軽重などの具合も自己診断をして、近所のクリニックに行けば良いのか大きな病院で見てもらった方が良いのかという加減を、何となく判断できて診察を受ける場所を決めることが多いと思います。
また、多少の熱があっても会社に通勤したりする方も多い事から、そういった人は会社の近くの内科医院に受診することでしょう。特に自覚症状はなくても慢性疾患のコントロールのために通院を続ける中高年層の患者さんたちは、勤務先や通勤の経路に近いクリニックの方が通院しやすいですし、専業主婦や定年退職して自宅にいる方たちがクリニックで診察を受けたいと思った時は、自宅から近い場所にあるクリニックか商店街や駅前などの繁華街にあるクリニックに通うのが普通です。
どちらにも共通しているのが、あまり大きな症状が出ていない場合が多いという事です。
小さな子供を連れて行きやすい小児科医院の場所
ところが小児科医院に受診する患者さんは、赤ちゃんや小さなお子様ばかりですので高熱が出ていたり、ひきつけを起こしていたり小さなお子様の場合には病気の症状が劇的に発症してくる場合が多くあります。
そのような場合に通院しやすい小児科医院の場所というのは、自宅のある住宅地に近い場所で、駅近くの繁華街に入る手前の住宅街から商店街に切り替わるような中間地点にあたる場所が、車や人通りもそれほど多くなく一番安心して通いやすい立地となります。
小児科に通院する患者さんの多くはお母さんが子供さんを連れて受診に来ます。自転車やベビーカーに子供さんを乗せて通院することが多くなりますので、交通量が少なくて少し静かで落ち着いた場所でありながら、商店街にも近い便利な場所が小児科医院の開業場所としては理想的な立地と言えるでしょう。
感染症対策のための隔離診察室と導線の分離計画
医院に隔離診察室を設けることが常識
小児科に通院する患者さんの中には、手足口病やマイコプラズマ肺炎・ノロウィルス感染症やインフルエンザなどといった多種の感染症を発症した患者さんが来院することがあります。
そのような感染性の疾患を持つ患者さんへの対応策としては、従来から医院に隔離診察室を設けることが常識とされていました。
ところが、病院を始め特にビル診で開業した小児科医院の多くは、一般の患者さんも感染症の患者さんも同じ1つの玄関から出入りして来たのが現状です。
テナントビルの場合には、建物の構造的な問題があります。
テナントビルの1階で開業する場合には正面玄関とは別に勝手口のような裏口がある場合もあるので、そうした構造を持ったテナントビルの場合には、感染症の患者さんには裏口から入ってもらい、そこに隔離診察室を配置するという動線計画を作ることもできます。
テナントビルで一般の患者さんが感染症に
ところが、ビルの上層階で開業している小児科医院の場合には、通常の場合にはエレベーターホールに出た場所にクリックの玄関を作ることになります。そのため、当然同じ経路を一般の患者さんと感染症の患者さんが通ることになります。
またそこからクリニックの玄関を入ってからも、一般の患者さんと同じ受付で診察の申し込みをすることが多くあります。
受付の職員さんが患者さんの症状を聞いて、そこで感染症と判断されてからようやく隔離診察室に案内されることになるので、かえって感染を拡大させてしまうという結果にもなっていました。小さいお子さんの予防接種を受けに小児科医院に行ったら他のお子さんから病気をうつされて具合が悪くなってしまった。というお話はよく聞きます。
テナントビルでの動線分離
そのような場合に、エレベーターの利用経路までは分離できないものの、エレベーターホールからクリニックの玄関に入る時には、一般の患者さんとは別にもう一つ感染症の患者さん専用の出入り口を作ることが求められます。
そのようにクリニックの出入り口を分離することができれば、そこから先の院内の導線も完全に分離して診察から最後のお会計に至るまで、一般の患者さんとは分離したスペースで感染症の診療を行うことができるようになります。
動線分離のレイアウト設計ができる条件
ところがこのようなレイアウトを計画するためには、テナントビルの広さとしては、少なくとも40坪程度のスペースを必要とするので、都心の小さなビル診ではなかなか実現が難しい課題と言えるでしょう。
郊外の戸建て開業であれば特段の制約のない中でのレイアウト設計ができますので、患者さんの動線分離を計画するためのレイアウトは自由に計画できます。
ところが、都心のテナントビルでの開業では、初めから決められた玄関を中心とした動線計画をしなくてはなりません。
テナント室内への出入り口が2カ所あれば、感染症の患者さんの診療を完全に導線分離した中で計画できますが、そのような条件が整ったテナントビルはなかなか見つかりません。ですがもし開業場所の条件が揃ったら、出入り口から完全に導線分離した小児科医院を計画することが大切です。
予約システムの導入で混雑を避ける
最近では小児科医院に限らず、新規開業の際に予約システムやWeb問診システムを導入するクリニックが増加して来ました。
ここ数年のコロナ禍の中で、待合室の混雑を避けることで感染防止対策を徹底するクリニックも増えてきました。
小児科医院に受診する患者さんは冬場には多くの患者さんが来院して、待合室は大変混み合ってしまいます。そのため診察を受けるまでに数時間も待たなくてはならないこともよくありました。その間、お子さん達はじっとしていられません。絵本を読み聞かせるなどしても限界があります。
また、感染症も含めて多くの患者さんが待合室で待機することで、院内感染も発生するリスクが高くなっていました。以前はそのような状況を気にかける医師は少なかったのですが、コロナ禍で患者激減の直撃を受けた小児科医院は感染症患者の導線分離と、待合室の密を防止する目的の予約システムの導入を積極的に進める様になってきました。
また、キャッシュレス決済の導入によって現金を介した感染リスクを軽減するだけでなく、クリニックにおける現金管理の業務を削減できる様になりました。
今やキャッシュレス決済は、新規開業のクリニックには欠かせない支払い方法となってきました。
小児科医院のレイアウトで配慮すべき点とは?
小児科医院のレイアウトを計画する中では、他の診療科と異なる特徴的な部分があります。
まずは、お母さんが子供さんを連れて通院する際に必要な自転車置き場です。
多くの患者さんは小児科医院がある地域の近所から通院してきますので、お子さんを自転車に乗せて来院するお母さんが大勢います。また、赤ちゃんをベビーカーに乗せて来院するお母さんもいますので、クリニックの玄関近くに自転車やベビーカーを置いておけるスペースを用意しておくことが必要です。
また、以前の小児科医院では院内に入ると多くの子供たちがプレイルームで遊んでいたものですが、コロナ禍の時代を経てプレイルームに置いてあったオモチャや絵本、アニメのCDなどが感染防止の観点から撤去されて、プレイルームで遊ぶことさえ禁止されてしまいました。
しかしながらコロナが落ち着き、日常が戻り始めた今は、またプレイルームの必要性が高まってきました。
また、コーナーとして必要なのが授乳室です。小さなスペースで良いので母乳を与えたり、粉ミルクを溶かすようなお湯と、哺乳瓶の洗浄ができるような給排水の設備があるとお母さん方に喜ばれます。
もう一つあると喜ばれるものがベビーベッドです。オムツ交換台は通常患者さん用のトイレの中に折りたたみ式の製品が取り付けられますので、待合室にベビーベッドが置いてあると赤ちゃんの休憩用のベッドとして重宝されます。
当社の開業コンサルティングをご利用いただいた方には、お母さん方に喜ばれる小児科医院のレイアウト設計にも対応いたします。
血算・CRPなどの緊急検査機能の装備
これまでの小児科医院というと、一人用のネブライザーなどはよく見かけましたが、それ以外にはこれと言った医療機器がないというクリニックが普通でした。
ところが最近では、全血球計算(血算)・CRPは院内で検査できるように開院の当初から導入する小児科医院が増えてきました。
また、小児科と耳鼻科には疾患に共通する部分が多くあるために、耳鏡や耳鼻科用のファイバーを導入して、患部の映像をお母さんに見てもらいながら病気の状態を説明することで、治療の過程をお母さん方によりよく理解してもらうと言う小児科医院も多くなりました。
少数ですが、成長外来を専門とする小児科医院の場合には院内にレントゲン装置を装備する必要があります。目的としては、手のレントゲン撮影をすることで骨の成長の具合を測定します。その場合には子供さんの手の骨のレントゲン撮影が主たる目的ですので、内科で使用するような大きなレントゲン室は必要ありません。
そこで小児科に装備するレントゲン装置は、耳鼻科で使用しているレントゲン装置を転用することが最も有効な手段となります。
この場合にはレントゲン室として必要な面積は、縦横1.5メートルのボックスタイプのレントゲン室を計画すれば十分に機能を果たすことができます。
この耳鼻科用のレントゲン装置を使用して、立位であれば胸部と腹部の撮影も可能です。
ちなみに、一般内科で必要なレントゲン室の標準的なサイズは、縦2メートル、横3メートルの大きさが必要になります。特に都心のクリニックの中で計画しようとした場合には、かなりの面積を占めることになりますので、このような装置を小児科医院に計画することは不適当と言えるでしょう。
小児科クリニック開業コンサルならオクスアイ
小児科医院を開業するときの注意点等をご紹介しましたが、開業準備では他にも資金調達や申請書類の提出など、たくさんのことを考えたり、行動したりすることが必要となります。それらの内容は、初めてのことばかりですので、ストレスもかかることでしょう。
病院で勤務医を続けながらの開業準備は、何かと難しいものです。そこで、当社のような小児科医院開業コンサルティングのご利用をお勧めいたします。
そして何よりも大切なことは、開業した小児科医院が集患できることです。そのための立地条件についてご紹介しましたが、他にも入念な経営計画が大切です。当社では、先生のご希望に沿いつつ、開業成功を目指した医院の経営計画立案をご支援いたします。
当社の特徴は、次のコンサルティングサービスに示すように、クリニック開業までのすべてのコンサルティングをワンストップで行えることです。また、医療機器をメーカから安く買い入れる方法や、電子カルテの選び方など、細かなところまで対応いたします。
小児科医院の開業をお考えの方は、まずクリニック開業成功のポイントを知ることができる開業セミナー&相談会(無料)にご参加ください。